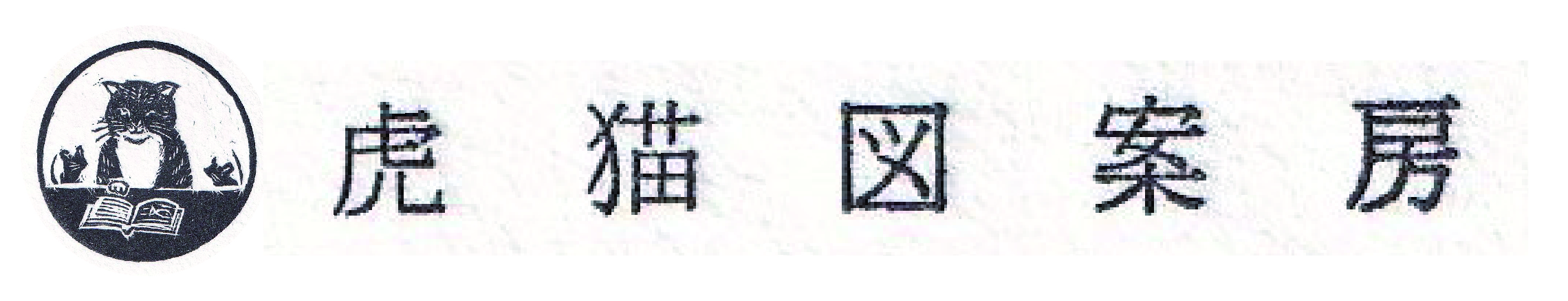早材と晩材・心材と辺材

写真は、先日山の中に切り出されて置いてあったヒノキ材。遠くからいい香りがして、近づいて顔を埋めてしまいました。
森林インストラクター受験生で、木口木版画家(※)というのは私だけではないでしょうか。
また、木口木版画をやっている人の中でも、私のように版画より木に興味があって始めたという人も少数派かもしれません。
(※差し支えない場所では木口木版画家を勝手に名乗ってしまうことにしました。でないと多分一生、名乗る許可を他人から与えられることは無い気がして。)
木口木版の場合、新しい版木に向き合う時はいつも、成長輪(年輪)と向き合うことになり、多くの場合に版木は自分よりも年上です。
直線をすーっと彫っていく時など、あぁ、何年分を横断している・・と考えます。
ちなみに木口面以外の木材の断面の方向性としては、いずれも縦方向に、柾目面(放射断面)と板目面(接線断面)があります。
浮世絵などをはじめとする木版画は、この縦方向の断面に絵柄を彫るものなので、輪としては見なくとも、線で年数を感じている木版画家さんもいらっしゃるのかもしれません。
「林業」の試験科目には木材に関する出題範囲があり、その中には木材の断面に関することも細かく含まれているので、これはもし出たら落とすわけにはいきません。自分の復習のためにメモします。
――――――――――――――
木口面を見た時に見える輪を成長輪といい、1年で出来た成長輪を年輪という。必ずしも1年で一つの輪にならない場合もある。
例えば熱帯など、季節の変化に乏しい地域では年輪が出来ない。また「重輪」など1年に2つ成長輪が出来る場合や「偽年輪」といって台風などで成長が止まったりしてあたかも1年が終わったかのように見える場合もある。成長輪の境がきちんと見えるのは、早材と晩材の色のコントラストのため。
早材:春、成長初期に形成される細胞。細胞の形が大きく壁が薄い。
晩材:夏、成長後期に形成される細胞。細胞の形が扁平で壁が厚い。早材よりも密度が高い。
通常は、早材と晩材の1セットで1年と見る。
――――――――――――――
木口面で見た時に中心部分を心材、外側部分を辺材という。心材は生きた細胞を全く含んでおらず、辺材もまた、成熟を完了すると死細胞となり心材となる。移行期にある材を移行材という。(樹木の細胞は外側から内側に向かって死んでいくということ、という理解で良いか?)
辺材部分は、(広葉樹の場合は)道管によって、根から水分を吸い上げて葉に送る水分通導の機能を持つ。心材部分はその機能は持たない。
樹種によっては、色の濃い心材と色の薄い辺材の境界が明瞭である。(明瞭:スギ、カラマツ、クリ、ケヤキなど / 不明瞭:ヒノキ、クスノキ、ハリギリなど)色の差が少なく区別出来ない樹種もある。(モミ、トドマツ、ツガ、サワグルミ、イタヤカエデ、トチノキなど)
心材に色が付いているのは、柔細胞が蓄えていた養分が、抽出成分や色素などに変化して材の中に沈着するためである。
樹幹の中で、心材は円錐形に存在する。
――――――――――――――

今制作途中の版木。これはツゲですが、このサイズで私の年齢はゆうに越えています。どこに生えていた?どんな光を浴びていた?こちらも真剣に向き合わなくてはと思います。