センスオブワンダー

6月あたま、優雅に舞うジャコウアゲハのカップルを見た。その周囲の樹木には彼らの好物、ウマノスズクサが絡み付いている。納得。
翌週、カップルの姿は無く、ウマノスズクサには不思議な形の花が咲いていた(写真)。
さらに2週間後、花は無くなり不思議な形の実がついていた。スターフルーツみたいな形の実。食べられたらいいのに。
さらにひと月後、ウマノスズクサの葉にはジャコウアゲハの幼虫が乗っていた。(←すごい形、すごい色。トゲトゲのウミウシみたい。)
ジャコウアゲハの幼虫は、ウマノスズクサの葉しか食べないのだそうだ。
一連の流れに無理なことがひとつもなくて、ちゃんと自然が流れている。

春、池にいた卵はカエルになり、茂みを跳ねていた。もう何もいないだろうかと見に行ったら、池に張り出す枝に5cmほどあるヤゴの抜け殻。(写真)
よく見ると、小さな池に一本だけ張り出した枝は脱皮組に大人気なようで、ヤゴの下にヒグラシ、そして違う種類のヤゴ達の抜け殻が連なっていた。
池には飛び回る大きなトンボの姿。トンボの種類に詳しくなくて分からないのだが、シオカラトンボのような大きさで、もう少しメタリックな感じ。少しだけ青色の入った銀色。大昔の巨大トンボも脱皮をしたのだろうか?と想像してしまう。
そして、この池の周囲でも、無理なことが起きずに自然が流れている、そんな感じがした。
さらに歩みを進めるとドドドという重低音。まずい、猪か?と思い棒立ちになってしまっていると、目の前の茂みから左右に分かれて鹿のカップルが飛び出して来た。ここは以前にも鹿に出会った場所。針広混交林なのだが林床のアオキがすっかり鹿の顔ぐらいの高さで食べ尽くされているエリア。これも自然の流れの一環として見るべきか。鹿の害による表層崩壊がニュースになって久しい。この地点も、柵をめぐらすなどしないと、土が剥き出しになりつつある。
今回森林試験の林業講義、6名の講師のうちお2人が、レイチェル・カーソンの「センス・オブ・ワンダー」について言及されていた。自然や未知のものに神秘さや不思議さを感じ、驚きや感動を覚える感性は全ての人が生まれながらに持っているもの。自然を見ていると、大人になって失ったその感性も少しは戻ってくるのかもしれない。そうすると、無理なほうへ無理なほうへと進みがちな人間の行動が見えてくるかもしれない。
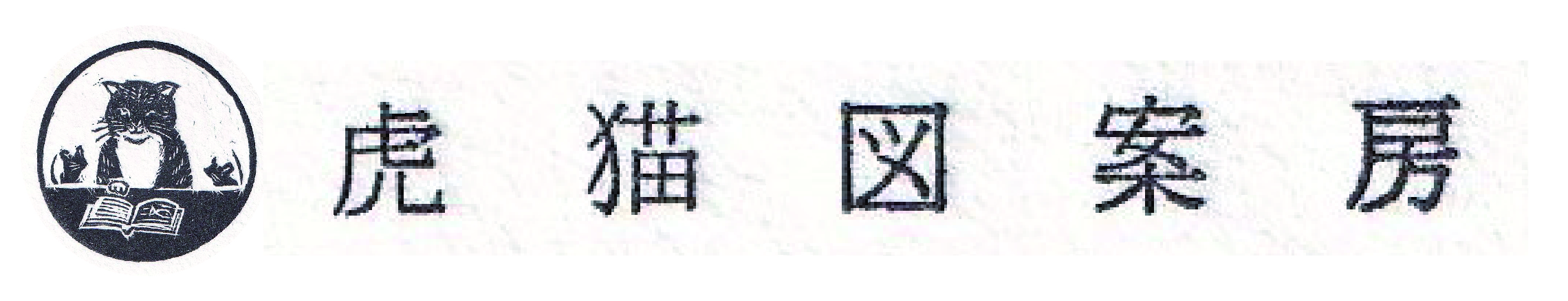


センスオブワンダー いいですよね 昔
若い時よみました写真もいい
うちも様々な昆虫が来ます ネズミもいます それらのものと一緒に暮らしていくのは大変
でも楽しいですね
子供の頃23件 離れたところのおばあちゃんとその孫と山に行った時はとても楽しかったです この草は食べられる これはだめだ これは何々に使えるとおばあちゃんが細かく教えてくれました 食べられるものと食べられないものについては 特に詳しかったです 鹿は、 ジギタリスという毒の草は食べないそうで 廃村になってしまったところにその草がたくさん生えているという話がありました
難しいですね 共存していくというのは
神奈川県は、台風がそばを通るので、雨と風がきそうです。嬉しい。