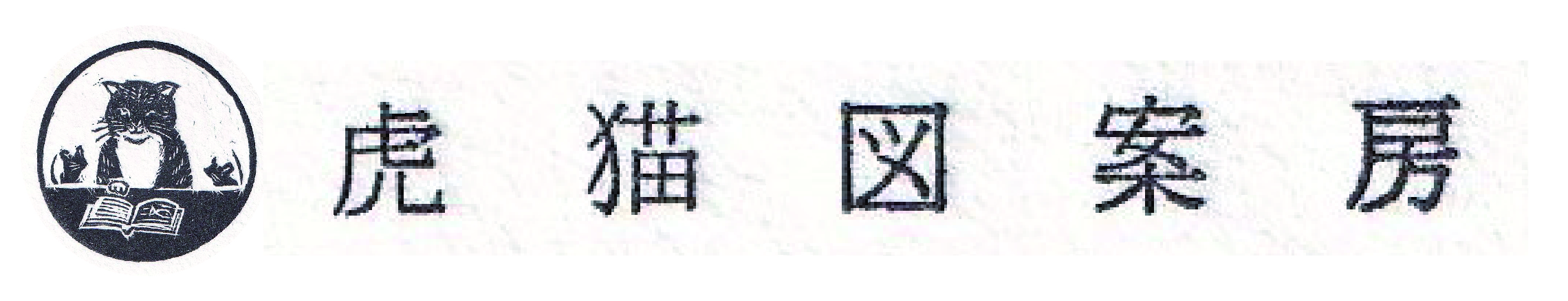二年目の一次試験を終えて

先月末、森林インストラクター資格試験を受けた。一科目再受験、二年目。とにかく無事に到着・帰宅出来たので良しとする。遅れがちな路線の住民なので、朝から絶対に外せない用事が都内である時は前泊。今回は神保町に泊まり、書店の誘惑に惑わされないように気をつけた。
肝心の回答のほうは、聞いたことの無い言葉がいくつかの問題にあった去年よりは、マシだったかと思う。しかし、何度もテキストで見たはずなのに答えが思い出せないとか、もうこれは自分の気合いの問題に依るという後悔はあった。果たして今年は二次試験に行かれるのか、ゲン担ぎに手帳には二次試験の予定を書き込む。
それにしても、80分で選択・穴埋めに加えて合計1200字ぐらいの記述があるというのは、なかなか大変。今年も最後まで時間を使う感じだった。手が痺れるし頭も限界。自宅でオンライン回答やマークシートが主流な世の中、会場運営や採点側もとても大変なことだと思う。
ざっくり言うと、木材資源の循環のことや、山村の抱える過疎のこと、昨今の山地災害のこと、針葉樹と広葉樹の細胞のこと、森林を伐採するまでの一連の作業のこと・・・そんな感じのことを、ひたすら文章で書かねばならず考えている暇などはなかった。去年は終了時間までかかったので、今年は余裕を持たせようと思っていたら今年もギリギリ。(来年受けることになってもギリギリでしょう。)
合否が分かる11月頭までは何も考えずに暮らそう、と思っていても、あそこの文章の頭と終わりが合っていないとか、回答を書き間違えたとか、今頃思い出した答えとかが浮かんでしまい、我ながらダメだなと思う。こんなことでは、まだまだ・・・
しかしどうであれ試験後の丸2日は心身の回復に充てると決めていたので、家の近くで見たかった映画と展示を見に行った。
これが両方ともあまりにも素晴らしく、心身の回復目的だったのだが、自分のこの後の人生をどう生きるか含め、真剣に考えさせられるものになってしまった。
◆映画は「炎をつなぐ」。
日本の職人達のドキュメンタリー。
見終わって、自分の手を見る。
例えば70歳、80歳になった時(無事になれたとして)、自分の手はどんな顔をしているだろうか?スマホやパソコンを使ってばかりのきれいな手でいたくない。(今も同世代からは手の劣化具合に驚かれるので、そんな心配はないけど。)この仕事をし続けたがために指や爪の形が変わっている、荒れている、そんな手を見るのが子どもの頃から好きだった。
映画のテーマにもなっている和蝋燭の灯心は、灯心草をよって作ったものだが、その周りにごく僅かに真綿が巻いてあることは、どれだけの人に知られているのだろうか。
その真綿は、養蚕農家が大事に大事に蚕を育てて作り、和蝋燭の原料となる櫨の実は、高い櫨の木に高齢のちぎりこさんが登って採取する。蜜蝋をとるために蒸された櫨の実のかすは、藍染の藍の瓶の温度を保つために使われる。色んなものが循環していた。
和蝋燭の灯心は、和蝋燭以外に、奈良の墨屋さんでも菜種油の中に浸して使われる。そこから煤を取り、その煤を集めて墨にするのだ。
漆、和紙、金箔・・・その他にも沢山の職人さん達の仕事を見ることができたが、とにかく、すぐに出来る、簡単に出来る、身体を酷使せずに快適に出来る、ということがひとつもない。そして何より、自分側の予定ではなくて、自然側の予定に合わせて日々が回っている人たちばかりだった。私にはそれが羨ましい。簡単に羨ましいなどと言ってはいけない大変さだというのは映画を見て分かったが、人間としてそれは正しい生き方の一つに違いないので、いいなと思う。
「毎日、毎年これを繰り返す」という仕事が何代も、何年も続いている。自然の中で繰り返す仕事。
若者が継がない、村を出ていく、需要が無い、良いものと分かっていても高いから買わない、、と、それらの仕事が廃れる原因は様々だ。
東京とやらはそんなに魅力的か、生きていくのはそんなにお金がかかることか、安いのは本当に良いことか。
最近、自分の制作に手を動かすよりも、なんだか根本的なところを色々考えてしまって、作品がはかどらない。
◆美術館のほうは「上田義彦展」。
すごい具象画を見ると、写真みたいと思うのに、すごい写真を見ると、絵みたいと思うのは何故。
写真と絵の関係ってなんだろう?
一連の写真を見終わった後に、インタビュー映像があって、そこで展覧会のタイトルの「From the Hip」という意味が分かった。
作品にするのには考えなければいけないが、写真を撮る瞬間を考えてはいけない、直感に従う。瞬間を逃すな。
瞬間が本当に抽出されたかのような感じだから、上田氏の写真は静けさを生むのかと思った。
たとえ人が写っていてもガヤガヤしていないというか。適当に切り取ったら、ガヤガヤしてしまうのではないか。
どの写真も、しーんと静まりかえっている。
骨の写真も、人の写真も、花の写真も、森の写真も、しーんとしている。
それが私にはとても良かった。
額装も良かった。ファインアートとはまた違う、デザインっぽい感性で、自由に収められていたように思う。
昨年の試験後には田中一村を見て回復したけれど、今年もまた、良いものを見ることが出来た。
写真は先日見たきのこ。名前がわからない。この時期、食用可とされているきのこも沢山自生しているのを見るのだけど、確信が持てず、写真に撮るだけ。食べる用は山の近くのお店で買うことにしている。昨日は「アシナガ(ナラタケ)」を買って下処理をし、栗と煮て食べた。昨年は「ハナイグチ」も沢山食べた。これもとても美味しい。
ミズナラの根元に出ると言われるマイタケをいつか見つけたくて、ミズナラの樹木を見るたびに株元を物色しているのだけど、未だ出会えていない。(マイタケの語源は、昔の人がその美味しさと貴重さに、見つけると舞を舞うほどだったことから、と森林テキストに記載あり。)